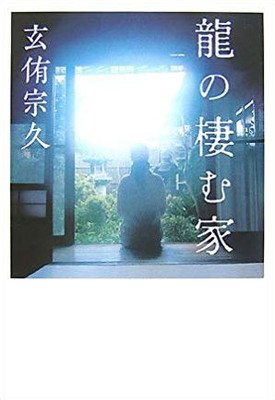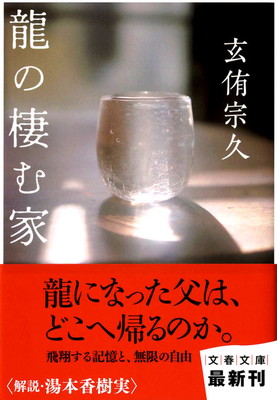上野でフィラデルフィア美術館展をやっているというので、身支度を調えて前傾姿勢で出かけていった。どうして前傾姿勢だったかというと、館内でレンタルできる音声ガイド(イヤホン式)の声が、檀れいさんだと新聞広告に書いてあったからだ。僕は檀れいさんが大好きなのだ。――が、美術館に到着し、入り口周辺に貼られたポスターを確認してみると、どうやら展示は印象派の絵が中心らしい。やはり音声ガイドを聴くのはよしておこうと僕は思い直した。せっかく印象画なのに、解説されたら意味がない。そんなものは出された料理をもう一度食材に戻されてしまうようなものだ。いや、もしかしたらそういった趣旨のガイドではなかったのかもしれないが、レシーバーの貸し出しを断ってしまったのでわからない。ごめんなさい檀れいさん。
そんなわけで、名だたる印象派たちの高級料理を心ゆくまで味わい、満腹感に恍惚としながら帰宅してみると、アマゾンで注文しておいた玄侑宗久さんの「龍の棲む家」(文藝春秋)が届いていた。待ちに待っていた新刊だ。コーヒーを淹れ、姿勢を正して表紙をひらき、一行一行を丹念に読みはじめたのだが――ああ、なんという偶然。
ここにも素晴らしい印象画があった。
決して長い物語ではない。主要登場人物も僅か四人で、主人公と、彼のお兄さん、介護職を辞した女性、そして痴呆老人。しかし、そこには紛れもない人世縮図が描かれていた。印象派の画家が、風景から感じ取った単純な線をキャンバスに落とし込んでいくように、著者は人間の成長、そして老いを、印象的なエピソードと会話によって僅か一五六ページの紙面に描き出していた。
実人生とすぐれた小説の関係は、写真と印象画の関係に似ている。
「龍の棲む家」を読んだ数時間で、僕は自分ではない人生を確かに生きた。人間の脳味噌がいつか退化して、一冊の小説を読むのに一生かかってしまうようなことにならないかぎり、きっと小説というメディアは大きな存在価値を持ちつづけるだろう。
2007/12/14日刊ゲンダイ 週間読書日記
書籍情報