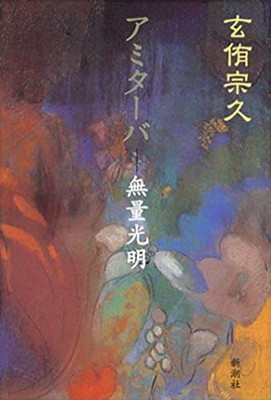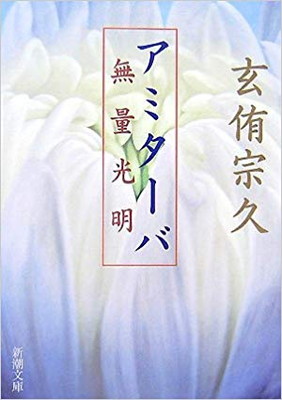タイトルの「アミターバ」とは「阿弥陀」に通じる言葉で、「無量の光」に満ちた極楽浄土のイメージを表しているらしい。
八十歳を目前にした老女が肝臓の胆管部の癌に冒される。生存率がほとんどゼロの難しい部位である。私の友人もちょうど同じ癌で四十代の若さで死んだ。病の進行とともに、彼女の意識はゆっくりと生の現実から、時間の統合が失われた混濁状態へ移行していく。その過程をこの小説は、老女を通して迫真の精密さで語っていく。
大阪で長いあいだ暮らした彼女は、東北の寺の僧侶に嫁いだ娘のもとに身を寄せている。婿の僧侶はよく義母に尽くし、死をめぐる彼女の問いかけに、教理どおりの説法ではなく、理論物理学の知識や他の宗教の教えも交えて、懸命に迷いながら答えようとする。その宗教と理知に立った彼の言葉と、大阪弁の軽口交じりの老女との言葉のやりとりが、とてもバランスがいい。現役の僧侶である著者の、いってみれば僧侶としての専門知識の部分と、作家としての想像力の部分が、がっぷり拮抗しているのである。
やがて老女が現実の肉体と時間の束縛から解放されてゆくにつれて、この小説は誰にとっても未踏である死の世界を、むせ返るような鮮明さとまぶしさで如実に描き出していく。この世で縁あった者たちと過ごした記憶が、次々と現れては消え、渾然と融け混じっていく。死にゆくときの意識とは、まさにこんなふうではないかと思えてくる。じっさい読んでいると、自分がいつか迎えるその時に浮かべるかもしれない映像が見えてくるのだ。父、母、子供たち、あの世この時の会話と表情、目に焼きついた光景、それらが地下水のように内側からあふれ出てくる。
「太陽と死は直視できない」とラ・ロシュフコーは述べたが、この小説は死を直視するばかりでなく、まざまざと「体験」させてくれる。その結果導かれるのは、死は怖くない、という確信に似た思いである。
本書によって死の恐怖や悲しみから癒される読者は少なくないはずだ。感動的という以上に、究極の救いの小説といえるだろう。
2003/06/29日本経済新聞
書籍情報