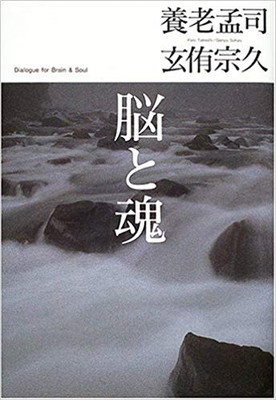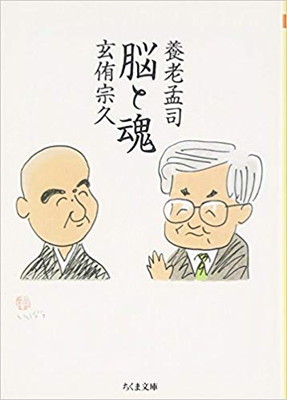養老孟司は解剖学者(東京大学名誉教授)、玄侑宗久は臨済宗僧侶で、平成十三年に『中陰の花』により芥川賞を受賞した作家である。本書は、「観念と身体」「都市と自然」「世間と個人」「脳と魂」の四章からなり、書名はその終章から採られている。
これは、昨年三月と八月に行なわれた博学多識なお二人による対談の記録だ。解剖学や仏教にまつわる話もむろん出てくるが、もっと、広範囲にわたる一種の文明論であり、時代の最先端の思想が平易な言葉で語られている。
ユングの共時性、シュレーディンガーの波動理論、ハイゼンベルグの不確定性理論、ボームの全体性、荘子の超越的平等思想などが縦横無尽に飛び交って対話が進んでいくのは壮観というほかない。
「心は一方では日常の関心事に向かうし、もう一方では『霊』の世界へ向かう」と、カントは述べた。ここでも、身体、都市、自然、世間などという日常の関心事がまず語られる。しかし、終章で記憶や魂に話題が移ろうとすると、ユングと違って、「細胞の連携」とか「最もよく出来たシステム」という術語が出てくるにすぎず、魂は語られない。電子顕微鏡で、細胞の中まで覗(のぞ)いてみても、精神構造は見えないからだ。
一般に、魂は、人格の無意識の側面である。魂には、光に向かおうとする願望と、原初の暗闇から浮かび上がりたいという抑え切れない欲求がある。光が現れる瞬間が神であり、救いと解放をもたらす。
現代人の魂に関して、解剖学という唯物的とも思える学問と、宗教といういわば対極にあるように思える思想とが、どこまでメスを入れうるのか、というのが読者の期待であろう。野次馬的な興味は、人間の限界を知らされることになり、がっかりする人もいるかもしれない。
だが、対談を通じて、仏教に培われた日本人の心性が明らかになるのは、収穫だった。
2005/02/07産経新聞
書籍情報