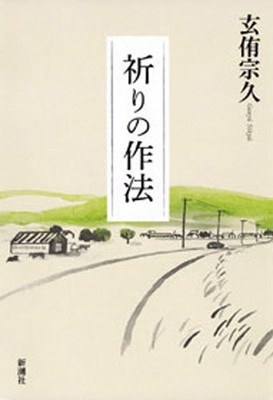福島県三春町に一禅刹を守る作家が、原発災害とたたかいつつある、中間報告である。
講演、ルポ、日記(三月十一日から六月二十八日まで)の三章からなり、どういう順序で読んでもよくて、右の逆順が分かりやすいかとも思うが、私は右の順で読み、深い納得をしたつもりでいる。
ただ、私はルポを読みはじめてすぐに笑った。国の内外から取材を受けるが、「福島」を一括りに概念化して質問する者が多い、と呆れている。私がここで思いだしたのは、沖縄の復帰前にしばしば「沖縄の八月十五日について」という原稿の注文を、その季節に受けて当惑したことであった。沖縄には組織的戦闘が終結した日としての「六月二十三日」があって、各人がその前や後に米軍に捕えられた記憶は切実にあるが、八月十五日を意識しなかった者が多い。そう答えて原稿をことわった。つまり、「復帰」を機に早呑み込みで本土と一括りにされる誤解を拒否したのである。
思えば諸種の誤解の拒否にむかって、沖縄評論は邁進したのであった。その沖縄の邁進の姿勢に、玄侑さんの文体がなんと似ていることか。沖縄の邁進の中身を木下順二は、「とり返しのつかないことを、どうしてもとり返すために」(戯曲『沖縄』)と書いたが、福島のそれも近い。
福島の災害の基礎条件は、まず「放射能」である。ベクレルとかシーベルトとかいう難解な語を、誰もが生き抜くために理解しなければならない。学のあるなしに関わりなく、県内の一切衆生を同時に同様に襲った大試練だ。そこに政府と東電が積み上げた解決への道筋を、誰もが疑いつつも一蓮托生で歩まなくてはならない。
この基礎条件の上で生き抜くのだが、その先で社会科学的な条件と闘うことになる。農漁民といわずサラリーマンといわず、大人も子供も災害を避けるために、生まれた場所を離れるかどうか、家族離散をどうするか、家畜を放っておくか、賭けることからはじまる。新しい悲劇の民話が生まれるかもしれない、前代未聞の民俗学の世界である。
この両者が絡み合ったのが、瓦礫の中間処理施設の立地の問題であり、農作物の県外移出にあたっての、風評被害の問題である。よそ者のエゴとの戦いの問題だともいえる。
玄侑さんの怒りの文体には、悲しみが流れながらも、以上の論理がしずかに見える。
日々、数多くの自殺の情報に接しつつ、職業としてお葬式に関わり、そのあまりの多さをも淡々と受け止めるなかで、地元の知識人として政府の東日本大震災復興構想会議に参じれば、使命感をもって当局の計画立案に参画したり、苛立ちをもって苦言を呈したりする。
(ここでも笑ったことがある。菅総理が釜石の避難所で壁の寄せ書きに「決然と生きる」と書いたのを、玄侑さんは嗤って、「これは偽政者ではなく、弱者である庶民の生き方を示す言葉」と書く。そこで私は思いだしたのだ。玄葉外相が普天間基地の辺野古への移設が捗らないことに手を焼いて、「踏まれても蹴られても」頑張る、と大真面目に言った。なにを気取っているか、それは沖縄が言うべき言葉だ、と嗤われた)
悲劇の構図もしかし、単純ではない。科学的危険を強調すれば、社会的差別を助長しかねない。世間に同調して原発をやめることは可能だが、低線量放射線とのつきあいは、どこに住んでも永遠にやめられない。
しかし禅師はここで、県民たちに「利他」「同悲」が目覚めたことを発見し、それを誇った上で、いまは「祈り」しかあるまいと、講演で説くのだ。じつは同じことがあとがきにも書かれていて、それはあとがきには馴染まないとも思われるだけに、よほど「祈り」にこだわっていると思しい。
祈りは俗には逃げとも受けとれようが、「無無明亦無無明尽乃至無老死亦無老死尽」(般若心経)と観ずれば、無限のたたかいが悟りに近づく─とはいえこれは、現地を見ていない評者の蔭ながらの期待にすぎないが。
2012/07/27波 2012年8月号
書籍情報