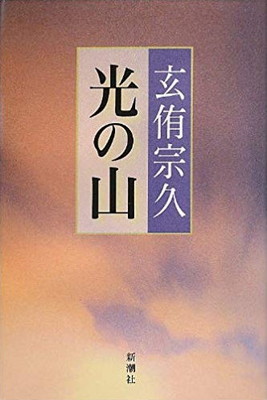福島に住まう作家・玄侑宗久が「東日本大震災以後、切実な現実の推移のなかで綴った」(あとがきより)小説集だ。全部で六篇を収める。「あなたの影をひきずりながら」「蟋蟀」「小太郎の義憤」「アメンボ」「拝み虫」そして代表作「光の山」。
著者の付した「あとがき」に興味深いことが書かれてある。ひとつは、作品タイトルに「虫」ばかり並んでいること。蟋蟀、アメンボ、拝み虫……なるほど。もうひとつ。作品集のタイトルを「裸虫」にしようかと思っていたということだ。人間を意味する「裸虫」は担当編集者の反対で実現しなかったようだが、要するに、「虫」に憑かれた小説集、といえる。ただ、著者はなぜ「虫」なのか、わからないと述べる。
震災や原発事故後の過酷な現実を生きる人々を写し取った小説がなぜ「虫」から離れられないのか。「拝み虫」を例に考えよう。
「山口がそのカマキリに気づいたのは夏の終わり頃だった」と書き出される小説の中で、主人公の山口は、妻の「聖子」を津波で亡くしている。津波が来るぞと電話で強く言ったにもかかわらず、聖子は笑い飛ばし、地震の後片付けをやっていたと思われる。気丈で明るい聖子の威勢のいい声が、カマキリの戦闘的な姿勢とどこか似ているような気がした。
山口は結婚式場を経営していた。人気があった。だが津波がすべてを破壊した。山口は仮設住宅に入った。入って一年後、胆管ガンとわかった。余命は半年と言われた。山口は除染作業に名乗りをあげた。
そんな折、医者の滝本が電話をかけてきた。滝本は東京の大学病院から救援に来た医師で、そのとき知り合った役場勤めの香奈と結婚する、という。しかも、香奈の住む「カセツ」で結婚式をあげたい、ついては山口に結婚式を取り仕切って欲しい、と。
山口は快諾し、小説の最後、仮設住宅で結婚式は行われる。だが式の途中、山口は意識を失う。救急車で運ばれる際、カマキリのことを山口は幾度も口にしたらしい。籠に入ったカマキリは見つけ出されたが、不注意から籠が落ちて、天窓が開いて、カマキリは籠から出てきたところを猫に食べられる……。
あっけなく、そして鮮やかな幕切れ。山口が亡くなった妻・聖子の面影をカマキリに見出し、カマキリを心の拠りどころにしていることは常識の範囲だろう。それよりもむしろ、「いまだに避難民と呼ばれる人々があとどれくらいそこに居るのかは知らないが、それは新しい集落というより態のいい収容所だった」といった断言のほうが読者の心に刺さるし、個人的には、こんな文章が見事だと思った。「墓地の側から見下ろす住宅群の全体が、ふと血流のよくない自分の肝臓みたいに思えることがあった」。原発事故によって避難を余儀なくされている人々の住む住宅を、自分の身体のガン化した部位と直喩で結ぶ筆には、踏み込んで書こうとする作家の強い意思が感じられる。
とすれば、カマキリと山口の距離感がやはり気になるのだ。虫と主人公の距離は何を意味しているのか、と。
一本、接線を引こう。
青来有一に「虫」という短篇がある(『爆心』所収)。長崎で被爆した「わたし」はいまでも夢にみる。原爆投下の直後、瓦礫の下に埋まっていたわたしに、「青々としたウマオイが、血だらけのふくらはぎをゆっくりと這って」きて、「葉っぱのように垂れた足の皮を、ウマオイは四角い口でもしゃもしゃと喰いはじめ」、「『まだ、生きておるね?』と無表情の大きな複眼で見つめて訊ねる」のだ……。わたしは被爆したあと、一人で生きてきた。好きな人はいた。他の女と結婚したその人とは一度、関係を持った。キリスト教に深く帰依していたはずの男は、その晩、こう語った。「おれらは虫といっしょさ。食べて、交わり、子を残していく……。誰が生き残り、誰が死ぬかは、ただの偶然でしかなか……それだけのことさ……」。二人の交わる姿は、ウマオイの影絵のようだった……。
あるいは原爆投下の瞬間。「瓦礫とガラスの間に飛び散った血の間で、たくさんの黒い蟻がしきりに走り回っていた記憶があります。わたしを運んでくれたのは、あれらの大群ではなかったか」と主人公は思い、腹のあたりでちぎれている死体には、もぞもぞ動く「サナダムシ」を見る。「樹木にも、家の軒下にも、地の底にも、ひとのからだの中にまで虫は棲んでいることを実感しました」と語る。
青来が描く虫と人間の距離は、小説に滲む独特の幻想性の中で、ほぼ消滅している。人間は虫であり、虫こそが人間である。そんな想定から小説は立ち上がっている。
一方で、玄侑宗久の描く虫と人間の間の距離は、こうした幻想性がないことに起因している。カマキリに妻を「感じた」程度でしかない。カマキリと妻は同じではない。同じならば小説は別のフェイズに移行したはずだ。著者はその距離の中に小説をとどめた。『福島に生きる』や『祈りの作法』といった著作は、「3・11」以後の現在の中で書かれている。それらは小説ではない。『光の山』は小説だが、あくまでも圧倒的な現実からのみ構成されている。
そして、その現実は人間の尊厳を損なうものだ。長崎の原爆と、福島の原発事故がともに、人間から大切な何かを剝ぎ取り、まさに「裸虫」に還元してしまうからこそ、虫が描かれるのではないかと思う。虫に憑かれるとはそういうことだ。
著者は、末尾の小説「光の山」で近未来を扱っている。放射能を浴びる山のツアーは、「一回り八十ミリシーベルトのコース」らしい。「透明で、清らかで、気高くて、しかも毒々しい」山には、シニカルに現実を逸脱しようとする書法がみえる。ここが突破口のように思えた。
2013/07/07文學界
書籍情報