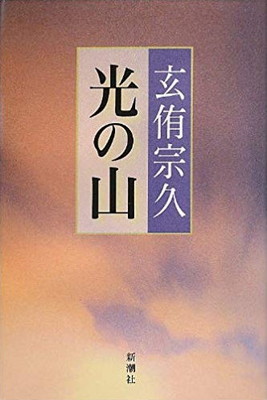東日本大震災のあと、あまりの惨状に文字通り絶句して、何ひとつ書けなくなった作家や詩人を私は何人も知っている。人類が解決できない放射能が拡散しつづけていて、家と家族と職業を奪われ苦しみ悲しむ被災者がいて、いまだ行方のわからぬ人がいて、それをおいそれと「作品」になどできようか─。そういう状況下で、私が真っ先に思い浮かべたのは玄侑宗久の存在だった。福島県在住の僧侶である彼は、死者を弔うだけでなく、どんな作家よりも身近に被災の実態を知り、切実な生々しい声を耳にしていたことだろう。そんな彼は周知のように、被災者の声を積極的に代弁し、行政との溝を埋めるべく政府諮問機関にも加わった。発言者、行動者としての彼の活躍を見守りながら、彼がどんな小説を将来書くのかを私はひそかに想像していた。「震災後文学」というカテゴリーが存在するとすれば、それこそは真っ先に中心におかれるべき仕事となるだろう、という身勝手な読者の期待とともに。
だが、それはまさに直後から書き続けられていたのである。冒頭の「あなたの影をひきずりながら」は雑誌『kotoba』の二〇一一年夏号に発表されている。執筆時期を考えると、まさにわれわれが絶句していた最中であったと推し量られる。わずか五ページに、家族でただ二人生き残りマイナス二度の避難所で肩を寄せ合う「お爺」と「お姉」が、週に一度帰ってくる東電職員の息子がレストランで焼肉定食を黙々と食べるのを見守る家族が、そして「お姉」が肺炎で死んだあと南相馬までふらり南下してきた祖父が、引きちぎられた断片のように描かれている。各場面を森進一の『港町ブルース』の歌詞が縁取るこの小品は、みごとな短編作品と称してかまわないものではあるが、どこかで「作品」に仕立てることをためらっているような、あえていえば罪深さを自覚しているかのような苦い寡黙さに包まれている。
「震災や原発事故以後の福島に住んでいれば、小説を書いてる場合じゃない、という声がどこからでも聞こえそうだった。私もだから「震災日記」や『祈りの作法』、あるいは『福島に生きる』など、被災地や福島の今を発信しつづけてきた。/しかし因業なことに、やはり私は放射線量にかかわらず呼吸しつづけるように、小説を書かないでは暮らせなかったのである。因業な自分を哀れとは思うものの、どこかで愛しいとも感じているようなので困ってしまう。」
震災直後から今年の春までの二年間かけて六編を書きつづけるうちに、ようやく「因業な自分」を「愛しいとも感じている」までになったのだというふうに私には読める。そして瓦礫の廃墟と化し放射能に蝕まれた故郷の大地にも新芽が生えるように、小説を書くという「因業」が、著者の内部で徐々に赦されて逞しく再生していくプロセスが、本書に見て取れるのだ。同時にそれは「絶句」を超えて、被災地の現実が著者の内部で少しずつ問いただされ、変容していった過程でもある。
僧侶の父子が自宅の二階部屋ごと津波で流される体験が描かれた「蟋蟀」には、テレビ報道に決して映らなかった凄惨な光景が点描されている。小説という架空の実況中継を通して再現された”あのとき”を、読者も一緒に目撃することになる。いわばここでは現場体験の純粋な共有が果たされているのだ。
「小太郎の義憤」は、地元の消防団員として防波堤の水門に向かったまま帰らなくなった父親の遺体をみつけるために、警察署でDNAの採取を受ける三歳の息子の話である。緊張のうちに無事採取の済んだ息子が、処置を施した目の前の警官に敬礼する。同じ年頃の孫とその母である娘を津波で亡くしている警官も、厳粛な顔で敬礼を返す。この場面の痛切さには肺腑をえぐられる。だが、この無垢な三歳児の「義憤」に表れた透明な怒りは、続く「アメンボ」では、にわかに屈折と濁りを湛えることになる。かつて「セシウム」という言葉に魅力を覚えていた女性が、震災のあと北海道に住みつづけている幼馴染みの親友と、お盆の帰省時に再会する。放射能から子どもを守るために遠方に移住した彼女は「あわせる顔がない」といって、般若の面をかぶったまま盆踊りに参加する。故郷を離れることができない者と、不本意に離れざるをえない者のあいだの残酷な亀裂が、ここには横たわっている。
いかに甚大な被害といえども天災である地震と津波に対して、明らかに人間の文明の生み出した人災である原発事故と放射能の恐怖が、透明な悲しみと怒りをどす黒く歪ませていく。「拝み虫」では、妻を津波で失い、おまけに胆管癌で余命半年と宣告された初老の男が、除染作業員をしながら「最後のご奉公」として、以前結婚式場を経営していた経験を生かして仮設住宅で知人の結婚式を執り行うのだが、そこには除染を巡る意見の対立と、きりのない作業に諦めが漂う現場も生々しく描かれていた。
放射能の人体への影響を巡っては、できるかぎり忌避すべきという厳格派から、低線量ならばむしろ健康に良いという「ホルミシス」派まで、極端な幅がある。その根拠も、二度の原爆投下とチェルノブイリ原発事故の被害の統計資料に基づいた類推にすぎない。定見なき政策に翻弄されながら被災地での日常は続いている。末尾の「光の山」の舞台は未来、東京にも大震災が起こり、富士山が噴火したあとの被災地を舞台とした恐るべき作品である。
行き場のない除染した土や廃棄物を自分の敷地に積み上げて山にした父のことを、老人が語る。彼の父は95歳まで生き、山上で焼いてほしいと遺言して死んだ。母と愛犬の墓も山上にある。その山がときおり妖しく燃え、瑠璃色の光を放つ。そこへ「ホルミシス効果」を信じる観光客がやってくる。一回り八〇ミリシーベルトのコースを、次のように彼は案内するのだ。
「おお、ご覧なさい。この世のものとは思えん美しさじゃ。透明で、清らかで、気高くて、しかも毒々しい。これが瑠璃色というもんなら、阿弥陀さんじゃなくて薬師如来のご来迎かもしれんな。おおお、土産物屋のネオンまで空に映って、これはもう東方のお浄土じゃな。」
このラストの口上は、もはや放射能に汚された島国に生きるしかない我々に突きつけられたグロテスク・ユーモアだ。しかし悪魔の悪戯のような除染土の山の光は、同時に荘厳な被災地の怒りと祈りの結集した火のようでもある。このようなヴィジョンにまで到達した本書は、単純に被災体験小説と括られるべきではない。だれも辿りつけなかった地平から本書は出現しているのだ。この怒りと祈りの先に、われわれは追い付けるだろうか。
2013/09/07新潮
書籍情報