本書は日本人の心がいわば型崩れを起こしつつある今、そもそも何が本来のかたちだったのかを確認する試みであり、作家と禅僧という二足のわらじをきっちりと履き、福島の寺の住職として原発事故の被災地にしっかりと留(とど)まっている著者ならではの興味深い日本人論である。
著者は、日本人は、何か大きな存在があっても決して絶対化せず、対になるものを生み出し、両方を認める傾向があるとして「両行(りょうこう)」(『荘子』の言葉)と呼び、認めるだけでなく両者を矛盾なくまとめあげていくことを「不二(ふに)」(『維摩経(ゆいまきょう)』など大乗仏教の言葉)と呼ぶ。
例えば仏教が入って来た時、それまでの古代信仰が「神道」というかたちを整えるが、しかしどちらかが否定されることなく習合されることで刺激しあいながら豊かになったこと、例えば天災の多い国であり、すべてを「無常」として忘れようとする方向と、「あはれ」と感じて忘れまいとする方向が対立しながらどちらもあり続けることで心の生産性がきわめて高まったこと等々、豊富な例をあげながら展開していく論は、賛否は別にともかく面白く読ませられた。
グローバリズムとナショナリズム、グローバリズムとローカリズムという現代の問題にも両行と不二の知恵が新しいものを産み出すのではないか、という著者の期待も、そうあってほしいと思った。
2013/12/15東京新聞
書籍情報
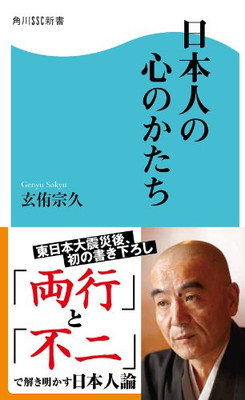
題名
日本人の心のかたち
著者・共著者
出版社
株式会社KADOKAWA
出版社URL
発売日
2013/11/9
価格
780円(税別)
※価格は刊行時のものです。
ISBN
9784047316249
Cコード
ページ
212
当サイトURL
