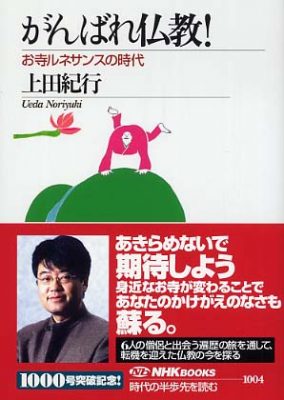以前、「がんばる」という言葉は嫌いだ、と何かに書いたことがある。それは「がんばる」という言葉にはどうしても「りきむ」印象があり、そうすると却って力が出しきれないと思うからだ。しかしこの本に込められた熱い思いは他に言いようがないようにも思える。効率的に力をだすことではなく、ここでは不器用でも「問い」のある「発心」と「行動」とが期待されているからである。
この本には私も紹介されているから滅多なことは言えないが、私の分を割り引いても、日本仏教に限らず、日本のこれからの在り方に明るい展望を与えてくれる本だと思う。いわば家族という単位が崩壊しつつある今、新しい共同体の在り方を現実的に提案しているのである。
ここで採りあげられた六人の僧侶は、じつは芽生えつつある新しい波の、軽い初動にすぎない。これから大きな波がくる、その萌芽というより、おそらく単なる巡り合わせなのだと思う。
たまたまそれができる境遇とご縁に恵まれた、それもがんばったからではなく、りきまずにできるほどに彼らには確信があったのだろう。彼らはいずれも「縁起」のなかに生きている。つまり普通は偶然として切り捨てられる出来事の連なりに意味を感じとり、そこに積極的に身を投じたのである。亡くなった有馬師だって今なお我々の踏みしめる縁起の世界を支えてくれている。共時的で相互的な時代の波に、彼らは素直だっただけなのだ。
六人の僧侶はいずれも宗派の枠組みを超え、場合によっては仏教というボーダーさえ超えてイヴェントによって新たなサンガ(共同体)を作ろうとした。大乗仏教が上座部の形骸化した教えに新たな命を吹き込んだように、今、新大乗とでも云うべき動きが起こりつつあるのかもしれない。
辛辣な分析も多い。しかし僧侶でもないのにこんなに熱く仏教を語る人が出現したことを、私はとにかく喜びたい。「仏教ルネッサンス塾」を主催する上田氏は、すでに新大乗の僧侶のひとりなのだ。
2004/11/01週刊ポスト
書籍情報