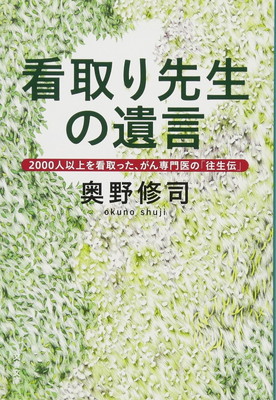久しぶりに充実した本を読んだ。
岡部健先生のことは、以前から聞き知ってはいた。この本にも登場する、東北大学の鈴木岩弓先生や、宮城県の金田諦應師などの口から聞いたのだと思う。
岡部先生が命名したという「臨床宗教師」のことも、あちこちから耳に入ってきていた。私はようやくそんな時代が来たのかと喜んではいたが、そこに岡部先生のどんな人生がどのように関与しているのか、詳しくは知らなかったのである。この本をまとめてくださった奥野修司氏に、まずは心から感謝したい。
岡部先生自身が胃がんになり、余命十ヶ月を告げられた事実から、第一章は始まる。この本が、いわば岡部医師の遺言であることが告げられるのである。
前半では、いや、全編にわたってだろうか、岡部先生自身が痛感している現在の医療の問題点、制度への疑問なども忌憚なく語られる。検診の意味と無意味、また特に抗がん剤という毒の扱いについては、一章を割いて力説されている。今や三人に一人ががん死するこの国では、殆んどの人にとって切実な話だろう。
問題の多い医療現場での経験から、岡部氏は「治せないがん患者の専門医になろう」と決意し、ついに県立がんセンターの医長を辞め、自宅で死を迎えるための「在宅医」に転じる。社会的な立場や収入のことを考えれば、蛮勇とも言える決断である。しかし岡部氏の堅い意志と迸(ほとばし)る情熱は、借家から始まった岡部医院の在宅緩和ケア活動をどんどん拡大していくのである。
宮城県内でのがん死者六二四〇人(二〇〇九年)のうち在宅死は六六〇人(一〇・五七%)だが、このうち約四割に当たる三〇〇人余りを岡部医院だけで看取ってきたというのだから、驚異的である。岡部氏の医療哲学が、まさに燎原(りょうげん)の火のように仙台界隈に広がったと言えるだろう。
岡部氏の医療哲学とは、端的に言えば、「在宅での死の看取りから生まれるタナトロジー(死生学)の形成」である。
ここ数十年の医療の変化、たとえばCT、MRIなどの登場は、敵を明確にして病との闘いを有利にすることには役立っても、最終的に向かうべき人の「死」に対しては何の指針も示してくれない。たとえホスピスであっても、そこには「死の不安」に対するケアプランがない。特にエヴィデンスばかり尊重する日本の医療においては、死を自然現象として捉える見方さえ失われ、最期の一定期間は「持続鎮静」というごまかしをせざるを得ないのが現状なのである。
そういえば以前、うちの檀家さんの死亡診断書の死因欄に、「自然死」と書いてあって驚いたのだが、なるほどその担当医師は岡部先生の一味であったかと、今になって思い返された。要するに、人はがんであっても手術や抗がん剤や点滴のせいではなく、がんそのものの進行によって「自然死」することができる。そのためのケアを今も最大限に試みているのが岡部医院なのである。
人が安らかに自然死するために、あるいはトータルペインの制御のためにも、「お迎え現象」が非常に重要な鍵になる。そう気づいたのも、岡部医師が見送った膨大な数のがん患者のお陰だろう。大勢の末期患者を見送るうちに、いわゆる「お迎え」が来ると穏やかに亡くなる人が多いことに、岡部氏は気づいた。社会学者の相澤出氏の調査でも、在宅で亡くなった人の四二・三%の家族が「そういうことがあった」と答えている。しかも不思議なことに、「お迎え現象」の起こった場所を訊くと、八七・一%が自宅、病院はわずかに五・二%だというのである。
このような現象は、医学的には「譫妄(せんもう)」などと処理され、これまでまともに扱われることは滅多になかった。しかし岡部氏は、これを死に近づく過程で起こる自然な生理現象と捉え、そこにこそ死という暗闇に進むための道標があるのではないかと考えた。なぜなら死そのものは見えなくとも、親しい人が「お迎え」に来て手引きし、案内してくれるのだからどんな闇でも心強いではないか。
そしてその非合理な手引きができるのは、宗教者しかいない。岡部医師のその確信こそが、現在東北大学で講座が続けられている「臨床宗教師」の発端だったのである。
思えば世界中の宗教が、暗闇としか思えない死後世界へのさまざまなビジョンを創出してきた。それが科学的に正しいかどうかを問い詰めても意味はない。最も科学的な態度は「わからない」に尽きるだろう。その上で、どのような物語に身を委ねるのか、表面的には我々個々人の自由のようにも感じるはずである。
しかし岡部医師も指摘しているように、我々の潜在意識(あるいはもっと深い集合的無意識)には、すでに信じるとか信じないという以前の深さで、民族あるいは人間としての認識や記憶(「識」)が蓄積されている。あらゆる知覚が外界の事物ではなくこの「識」に左右されるという仏教理論(「唯識無境」)を持ち出すまでもなく、殊に死期の迫った人々の変性意識に現れるリアルは、通常の意識の思い描く世界とは明らかに違う。意識の世界で「譫妄」とみなされることが、変性意識状態ではリアルなのである。
私は、二〇〇〇年に発表した『水の舳先』(新潮文庫)で、死に行く人々に訪れる一種の恍惚を描いた。キリスト教と仏教との区別を超え、死後世界へのビジョンと「水」への信仰があれば、そこにリアルな恍惚さえ感受できることを示したかったのである。
続く「中陰の花』(文春文庫)や『アミターバ―――無量光明』(新潮文庫)には、いわゆる霊異や「お迎え現象」などがふんだんに出てくる。当時の私は、それを「時間という最大で最後の煩悩から解放された状態」と捉えていたが、「集合的無意識が漏れ出る事態」と言っても同じことである。職業柄、そうした「お迎え」話や霊異譚に触れることは多く、私のなかでもそれは、変性意識下における代表的なリアルだった。
問題は、「お迎え」を受けてどこへ行くのか、ということだが、「あの世」という言葉の意味深長さには目を瞠る。まずこれは、特定の宗教用語ではない。仏教語と思っている方もおいでかもしれないが、仏教はあくまで浄土である。弥勒や薬師、阿弥陀などと所属はいろいろだが、すべて仏国土か浄土と呼ばれる。
「あの世」が意味するものは、誰も「どの世?」と訊かないところを見ると、よく知っている懐かしい世界で、「あの」で通じる場所なのだ。そうすると、浄土のように「往く」場所ではなく、「帰る」場所ではないだろうか。もっと言えば、人は「そこから来た」元の場所へ、最後に帰ろうと欲しているのではないか。たとえば『竹取物語』のかぐや姫も、自らがやってきた月を死者の世界だと告白し、とうとうそこへ戻っていくのである。日本人の死者がお盆などに戻ってくるのも、浄土というよりこの月のイメージが強い。だからこそお盆は旧暦の満月なのだろう。
浅学にして、私は「あの世」という言葉の創出者を知らない。いや、誰かそんな人がいたとも、思えないのだ。これはもしや、衆生の欲求がまるで集合的無意識のように、どこからともなく沁みだして出来た言葉ではないだろうか。
少なくとも日本人は、初めて往く浄土やキリスト教の天国よりも、懐かしい「あの世」に帰りたい。これは仏教徒でもキリスト教徒でも、日本人ならそうなのではないか。そしてもしかすると世界には、そのような考え方の根強い地域がもっともっとあるのではないだろうか。
ともあれ、「あの世」と「お迎え」は間違いなく連動している。最終的な到着地が懐かしい場所であることが、懐かしい人の登場によって無意識のうちに示唆されるのである。
私としても、特に『アミターバ』は死に行く旅路の道連れにと思って書いた。阿弥陀(無量光明)世界への旅路を途中まででも描き、少しでも不安が軽減できればと思ったのである。しかし岡部医師は現実の在宅医療の現場でそのことに奮闘され、その実践部隊としての「臨床宗教師」養成講座にまで繋げた。本当に凄い仕事をなさったものである。私とすれば、このアプローチが医療者側から成されたことに、驚きと喜びを禁じ得ない。昔ながらの安らかな死が、一人の医師の熱烈な働きかけで今後もじわじわと広まっていくことを願うばかりである。
先日、第三十九回日本死の臨床研究会の年次大会が岐阜であり、私も登壇して「浅き夢見し酔ひもせす」という演題で話した。端的に申し上げれば、「あの世」から見たこの世、覚めてしまえば夢と見做(みな)せるこの世と旅路そのものについての話である。
その内容はともかく、私はそこで懐かしい山崎章郎先生や柏木哲夫先生、そして郡山のホスピス、坪井病院の清水千世看護部長にも出逢った。あまりに懐かしくて、そこが「あの世」かと錯覚したほどだが、その会場には明らかに新しい「死の臨床」へのストリームが感じられた。そこここに岡部医師の名前が呟かれ、また「臨床宗教師」の活動も具体的に紹介されていた。私のところにも講演後、山口県の建仁寺派の若い和尚が、臨済宗最初の臨床宗教師だと挨拶に来てくれた。
また名古屋の看護介護の学校で、『アミターバ』や『中陰の花』をテキストに使っていると知ったことも嬉しかった。
楽観的にすぎるかもしれないが、「死の臨床」は明らかに岡部先生の志した方向に動きつつある。今後、介護と医療・看護との、制度上の連携など、国や厚労省に期待すべき課題も多い。また臨床宗教師の活躍については、「縁起でもない」と見られる壁も厚いし、まだ幾つものハードルが地域や病院ごとにあることだろう。しかしそれでも、この本に描かれた岡部医師の情熱の転写が、そう簡単に収まるとは思えないのである。
奥野修司氏が一七〇時間ものインタビューをまとめた内容は、むろんこの紙幅では語り尽くせるはずもない。特に彼が末期の時をすごした「岡部村」については、触れたかったが生半可に書くこともできず、諦めることにした。奥さまと息子さんの登場する家族としてのリアルな岡部氏の姿も含め、詳細はむろん読んでいただくしかないのだが、最後に言っておきたいのは、この本を読み、それぞれで自分や家族の具体的な死に方を考えてみてほしい、ということだ。財産整理などではなく、死そのものの在り方である。
おそらくこの本を熟読するだけで、がんや死への向きあい方が相当変わるはずである。この国に再び「看取りの文化」が根付き、読者の皆さんがいずれ「お迎え」を得てゆっくり安らかに「あの世」に旅立たれることを、厳粛にお祈りしたい。
あ、最後の最後にもう一つ。カール・ベッカー教授との対談にはこの本のエッセンスが全て凝縮されている。巻末でそんなふうに感じさせたのも構成の妙だろう。奥野氏や編集者のご苦労も偲ばれる、じつに見事な本である。
2016/01/10看取り先生の遺言 2000人以上を看取った、がん専門医の「往生伝」
書籍情報