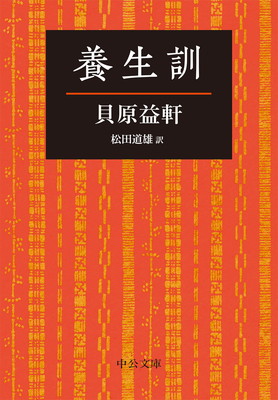私は以前、『養生訓』を中心にさまざまな養生法について考える本を書いた(『養生事始』清流出版、二○一二年)。きっと今回はそれゆえの依頼だろうから、その本にまつわる話から始めたいと思う。
サブタイトルは「自愛の手引書」としたのだが、現代人は本当に自愛の仕方を知らないと思う。「自愛」はもはや、手紙の末尾に書くだけの死語なのではないかとさえ思う。主に『養生訓』における自愛について、あらためて考えてみたい。
まずなぜ養生するのか、というと、益軒先生の場合はじつにはっきりしている。我々の身体は「天地のみたまもの(御賜物)、父母の残せる身なれば、つつしんでよく養ひて、そこなひやぶらず、天年を長くたもつべし」。つまり、養生することはそのまま「孝」であり、人の倫(みち)にも通じる。先生の自信満々の口調の背景にはまずそのことがあると知るべきだろう。
むろん、八十三歳で歯が一本も欠けておらず、視力の衰えもないというのだから、自信はあるだろう。しかしそれは、天を畏れ、我が身を慎みつづけた努力への自信である。だからこそ、先生は自信をもって我々にも禁欲と努力を勧めるのである。
長風呂はせず、酒も微酔にとどめ、しかも「冬温なることを極めず、夏涼き事をきはめず」(『千金方』)、およそ神経質なほどすべてに禁欲的なのである。そういえば見ることも用がなければ眼を閉じよと言うし、聞くことについても長く聞くなと仰っている。我が身はみたまものだから、借りものはなるべく傷つけずに返そうという感覚なのかもしれない。
それにしても、房事についての禁止事項には天を畏れる感覚が横溢していて驚く。日蝕・月蝕・雷・大風・大雨でもダメだし、大暑・大寒・虹や地震でもいけない。場所についても許されない所が列挙され、模範的な周期も示されるが、それ以前に房事が可能でしかも厳格に制約を課すべき状況を若い頃はひたすら羨んだものだった。「接して洩らさず」に到っては、贅沢以外の何物でもないだろう、と。
いま思うと、初めてこの本に出逢った若い頃には、あまりのストイックさに従いていけないという印象だった気がする。
当時の私は、高校時代にさまざまな呼吸法に親しみはしたものの、二十代前半にすっかり身体を放置し、精神に異様な軋みさえ感じていた。たまたま知り合った友達から導引を習い、ようやく身体の硬さを自覚してからは、京都までヨガを習いに行き、自分なりの自愛の仕方も考え始めた。しかしその時点ではまだこの本に出逢えず、私は臨済宗の修行道場に行ったのである。
あれはいったい何だったのだろう、というのが道場生活の正直な印象である。傍目にはとても自愛とは思えないだろうが、甘やかしていた身体が一気に嵐の中に放り込まれ、撹拌され、心さえ保てば身体はなんとか従いてきてくれるものだと知った。いわば身体の底力とでも言うべきか、自愛とはけっして甘やかすことではないのだと、その底力を感じつつ思ったものだった。益軒先生も「身は心のやっこなり。うごかして労せしむべし」と宣うが、全くそのとおりだと思ったのである。
しかし私はおそらくそこで、限界を試すような傲岸な所行まで自愛と思い込んでしまったのではないだろうか。
禅僧にとっては、呼吸法や瞑想、坐禅などが何よりの養生になる。そうした思いで接した『養生訓』はあまりにも細かいことに神経質だし、臆病にさえ思えた。確かに益軒先生は、道場での短い睡眠時間を肯定してくださってはいる。「ねぶりをすくなくすれば、無病になるは、元気めぐりやすきが故也」。私はこの言葉に膝を打ったものだが、要は道場での荒療治で俄かに元気になった私が、『養生訓』のあまりの細かさに距離を置くようになっていったのである。
しかし諸行無常と言うべきか、四十代、五十代、六十代と同書を読み返すうちに、私は益軒先生の畏れや慎みに深く感じ入るようになっていった。だいたい生きていくうえで不可欠な、歩き方、坐り方、眠り方から食事や房事まで、これほど網羅的にうるさく説いてくださるご隠居が他にいるだろうか。
なかには迷信だろうと思えたり、今では医学的におかしいという部分もないではない。しかしこれほど口酸っぱく禁欲と努力を迫るのは、ひとえに身体という自然への畏怖からであり、それは今、我々が最も取り戻すべき心持ちなのではないだろうか。
令和元年十月、台風十九号が大変な爪痕と死者負傷者を残して東日本を走り去った。私はこのとき被害甚大だった福島県にいて、つくづく我々の自然観そのものがおかしくなっていたことを自覚した。
明治以降、オランダから学んだ治水法は、とにかく水を川に封じ込め、「連続堤防」によって海まで運び出してしまう完全制御型だった。ゆったり流れるヨーロッパの川にはそれで好かったのだろう。
しかし時に滝のように暴れる日本の川には、江戸時代までは「流域治水」という考え方が採用されていた。武田信玄の信玄堤のように、ある水位を超えた水は堤防に入った切れ目から外に逃がし、いわば小さく負け続けることで大敗を避けるのである。切れ目の外には湿地帯や水田、あるいは遊水池が作ってあり、大量の水は流域全体で受けとめる。そこには自然がけっして勝てない相手だという諦念があり、畏怖しながらそれでも恵みを頂く相手とつきあう智慧が感じられる。
ああ、益軒先生の態度もきっとこれなのだと、私は氾濫する川の映像を眺めながら思った。そして自分も、いつのまにか西洋的な自然観、つまりコントロール欲求に染まりつつあったことを恥じたのである。
最近の長寿願望にはどうも欲望めいたものを感じる。飲食や睡眠などの快楽は充分に享受しつつ、サプリや薬で調整しようとする。むろん医学の進歩は無視できないが、各人が身体という自然に向き合う覚悟はどんどん減衰しているのではないだろうか。
自然は不自然も含みながら常に我々の想定を超えてくる。制御できると考える人々の科学や医学のさまざまな成果には素直に感謝したいが、結局のところ、死も含めた身体の自然は最終的には制御しきれないのである。
養生とは、脅威でありながら恵みを下さる相手との、畏れ多き道行きなのではないだろうか。
ならば自愛とは、自信をもって臆病に振る舞うことなのかもしれない。今後もどう変わるか分からないが、今六十三歳の私はそう思うのである。
最後に一つだけ、敬愛する益軒先生だが持ち上げすぎた気もするので苦言を呈しておきたい。導引をとても好まれ、足裏マッサージや腎臓マッサージなども毎晩されていたようだが、召使い・児童・童子などに教えてさせるというのは、そりゃあ、ズルイですよ。
自らも自愛しながら他からも養生してもらえる、昔のご隠居が本当に羨ましい。
2020/1/21中央公論新社 中公文庫「養生訓」 解説
関連リンク
書籍情報