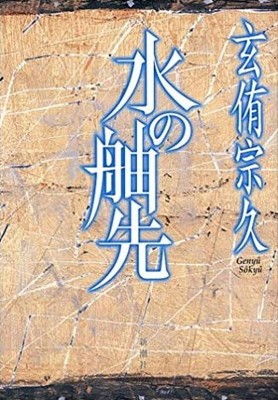かねてから疑問に思っていることがあった。日本の仏教者から現代社会に切り込むような発言が聞こえてこないのは何故か。新宗教はともかく、在来仏教からの発言は極めて少ない。仏教的見地から見たグローバリゼーションとか、仏教的教育改革案とか、提言があっても良さそうなものではないか。文学もしかり。五木寛之など在家の作家が仏教について書くことはある。しかし日本文化の基層をなし、これだけ数多く寺もあるのに、仏教作家が教団内から生み出されないのは何故か。
そう思っていたところに、現役の僧侶の小説家が出現した。玄侑宗久氏は会社勤めの後二〇代の終わりから仏門に入った、現在四〇代半ばの臨済宗副住職である。いかなる小説世界かと興味津々の評者を驚かせたのは、そのあまりの直球勝負であった。主人公は僧侶であり、彼は重い病を抱えた患者の集まる湯治場で、人の死に際に関わり、看取りと葬式を執り行う。僧侶である著者が、死と救済、看取りと葬儀の意味について書く。あまりにまっとうすぎて、どこにも逃げのあり得ない世界が小説のテーマとして選ばれているのだ。
それに加えて、著者は第二の主人公として、キリスト者の女性を登場させた。聖書を心の支えに、末期のガンを患いながら献身的に生きる美しき女性と、仏教に半ば醒めた疑問も感じつつ、看取りの意味について真摯に考え抜くひとりの僧。それは仏教者がキリスト者の救いを理解できるかという、宗教理解の問いを含みつつ進行する、仏の愛とキリストの愛の交点を探る物語でもある。
この愛の物語のクライマックスは、看取りのその瞬間にある。その半ばショッキングな情景をここに述べるのは控えよう。ただ、そこには何千回と葬儀を行ったであろう著者の透徹した臨終感がある。臨終とは送るものと逝くものの恍惚、エクスタシーの中にこそその本質がある。そして一見異教的なその恍惚にこそ、異なる宗教が歩み寄れる原初的救いの地平があるのだ。この作家からしばし目が離せそうにない。
2001/07/08読売新聞
書籍情報