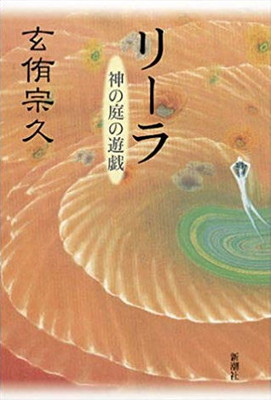独特の死生観を描いた魅力的な作品を世に送り続ける、“小説を書く僧侶”玄侑宗久氏。新作『リーラ 神の庭の遊戯』は、自殺と「共時性」がテーマの長編小説である。
自殺した二十三歳の女性・飛鳥。彼女と関わりのあった六人が、それぞれの視点から彼女との過去や自分自身を語るにつれ、死の謎や真実があぶり出されていく……。「自殺」は描き得ない。そう考えたという。
「自殺で身内を亡くした人は、自責の念から死の理由を追い求めようとします。しかしそれが完全に究明されることはない。なぜなら、自殺はロジカルでは突き詰められないものだからです。自殺しようとする人は、死に向かって着実に日々進んでいくわけではなく、共時的に起こってくる様々な事柄に背中を押されるようにして絶望に運ばれる―論理で説明できなくとも、小説ならばそれを伝えられるのではないかと思ったんです」。
輪廻転生、気など、それぞれの人の様々な考え方が描かれる。果たして魂は救済されたのか。そして「リーラ」(「遊戯」の意、サンスクリットの語幹は「揺れる」などと文中では語られる)というもの。
「偶然としか思えないようなことが重なって起こることがあります。その波に身を任せることは、現在最良の選択かもしれないのに、現代人は予定や約束などに縛られてそれができない。波に逆らうから波に呑まれるわけで、波に乗ろうとする人は、どんな大きな波が来ても平気なんです。ただ、思いもしないところに運ばれて、『あら楽しい』となるだけで(笑)」
なりゆきそのものを楽しむ。それが「リーラ」ということか。
「小説を書きながら言うのは矛盾かもしれませんが、言葉の呪縛から解放されなければと思います。それが『リーラ』の世界です。論理や思考といったものがいかに不自由か。論理につかまらない言葉であれば、言葉を使いつつも、その呪縛から逃れられるはずです」。
小説には「創造の現場」があるのだという。
「教養新書を書くときは、自分の思考の跡をたどり、論理で書き進めていきます。一方小説は、著者の論理を超えて自然に浮かんできたものが自然に成長していくさまを書いていく。それは、たった今創造されているものなんです」。
インタビュー中、強く共感を覚えた言葉がある。「読む側にとっては、新書は知識にしかならないが、小説は体験になる」。『リーラ』を読んでいる間、周囲が次第に無色無音の世界になっていく感覚を確かに味わったのだ。読む者の「魂」そのものが何かを受け止めざるを得ない、そんな作品である。
2004/10/01新刊展望(日販)
書籍情報