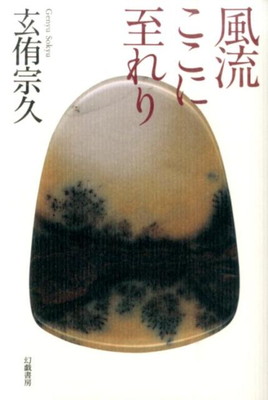宇宙というと、ふつうはOuter Space、つまり地球外の空間を想像されるだろう。しかし初めにお断りしておきたいのは、ここでの宇宙とは空間だけでなく、時間をも含んだ概念であることだ。
「宇宙」という言葉が初めて現れるのは中国の紀元前二世紀、漢の時代の『淮南子(えなんじ)』の第十一巻「斎俗訓(せぞくくん)」である。曰(いわ)く、「往古今来、之を宙と謂(い)い、四方上下、之を宇と謂う」。つまり宇は空間、宙は時間の概念。しかもこの両者は、繋(つな)がりのあるものとして当初から熟語化して使われてきた。
ギリシア語起源の「Cosmos」でも英語の「Universe」・フランス語の「Univers」でも、空間のみに過ぎないことを考えあわせると、これは凄(すご)いことだ。じつは西洋では、ニュートン力学以後も、時間と空間はそれぞれ独立した変量とみなされてきた。アインシュタインが出るに及んで、ようやく両者が相互に関連しあっていることが提示されたのである。
仏教の想定した宇宙はバラモン教以来の「ブラフマン(梵・ぼん)」だが、これはもともと宇宙の神秘力とでも言うべきものだ。当然、時間も空間も含んでいる。ウパニシャッド哲学では盛んに「梵我一如(ぼんがいちにょ)」が説かれるが、同じ一つの原理が、宇宙をも我をもあらしめている、ということだろう。ここでは仏教の想定していた空間と時間の成り立ちについて考えてみたい。
まず空間のほうだが、最大の空間は三千大千世界。ちなみにこの「世界」も「世」が時間で「界」が空間の広がりを意味する。この大千世界の十億分の一が小千世界、さらにその千分の一が一小世界という。三千大千世界を詳述するとあまりにベラボーなので、ここではまず一小世界の輪郭をご説明するのだが、小世界ひとつの中にも須弥山の上空に七層の天界が想定されている。その中間にある他化(たけ)自在天までの距離が、およそ四千四百八十万キロ。天辺の大梵天界までは約三億六千万キロである。ちなみに太陽は、地球からおよそ一億五千万キロの距離にある。当然そこではそれなりの時間も意識されているわけだ。しかし逆に、どんな距離でも一瞬に、というテレポーテーションも仏典には描写されている。
ともあれ、この一小世界の千倍が小千世界だが、専門家の計算によるとこの直径は、二十五×十の四十五乗光年らしい。さらにその十億倍が大千世界だから、二十五×十の五十四乗光年ということになる。
銀河系は、直径およそ十万光年のレンズ型だとされる。宇宙は拡大し続けているとしても、おそらく現在の宇宙物理学が想定する以上の空間を、仏教は想定したのである。
小さいほうは「極微(ごくみ)」が最小である。現在の物理学では、素粒子を想定しているが、ほぼ同じ程度の存在と考えていいだろう。素粒子を構成するものは、幾種類かのクォーク、あるいは振動数の違う「超ヒモ」などと考えられているが、仏教ではギリシャと同様、地・水・火・風のはたらきの組み合わせと考えた。この四つの機能が縁によって合わさることで極微ができる。つまり極微以下は、物質ではなく機能と考えたわけだ。極微が七つ集まると「微塵(みじん)」になる。
「五輪塔」を見ればわかるように、仏教ではこの地水火風のほかに、一番上に「空」が載っている。これは地・水・火・風に分離したあとの状態だからエネルギーと考えてもいいが、現代物理学が最近直面している「モノ」から「コト」への流れを、うまく説明してくれる。量子論もいうように、超ミクロの世界は観測されて初めて粒子が現れ、観測しなければ波である確率が高いという。つまり観測される事態は、観測する人との間に起こる「コト」なのである。すべてがそれ自体で独立した実在ではありえないという「空」の思想は、量子論を先取りしていたことになる。
時間が相対的であることは、仏教は当然のことと考えていた。一応最短時間の「刹那(せつな)」は七十五分の一秒。最長の時間は「無量劫(ごう)数」だろうか。一劫とは、一辺が七キロもある大きな岩に天女が舞い降りてくる。その天女の羽衣で石が摩滅してなくなるまでの時間だというのだが、天女が降りてくるのは百年に一度とも三千年に一度とも云(い)われる。いずれにしてもその無量倍だから、永遠といってもいいだろう。
そうしたマクロからミクロまでを、刹那から無量劫数のスパンで考えたのが仏教だが、梵我一如ということは、無限の空間と無量の時間とが、私という存在に流れ込んでいるということだ。現代科学はそれを遺伝子によって説明するが、仏教では「蓮華(れんげ)」というものを想定した。『華厳経(けごんきょう)』によれば、蓮華というのは全ての命がそこから生まれてきたという水中の白い花だ。これはどう考えても細胞核、あるいは遺伝子だろう。一に一切が込められ、一切に一が実現する。それも『華厳経』の言葉だが、それは遺伝子だけでなく、ホログラフィーという記録再生技術まで説明してしまうのである。
ご存じの方も多いかと思うが、ホログラフィーとは、三次元の情報を二次元に記憶させ、それにレーザー光線を当てて再生する技術だ。この場合、記憶媒体の二次元平面を百分の一にしても千分の一にしても、うっすらとだが全体が映るのである。つまり、ある平面のここにはどの情報という、局在的な記憶のされ方ではなく、一点に全てが記憶された無数の点の集合がホログラフィーだ。最近では、脳の記憶にもそうした側面があるとされる。これによって、草葉の陰に誰かの記憶がまとまって存在する可能性もでてきたことになる。
仏教は、いつだって「全体性」への視線を持ちつづけてきた。「色」という部分を見るのにも、常に「空」という「全体性」の反映を見ようとしてきた。それは、ミクロにもマクロにも「宇宙」を感じてきたからに違いない。
「範囲を限定して分析してわかる」という近代科学の方法を用いずに、直観的にここまでの宇宙を想定した人間の底知れぬ能力を、私は心から畏怖(いふ)している。それは仏教の手柄ではなく、斉(ひと)しく人類のもつ叡智(えいち)の所産なのだと思う。
2005/03/31AERA臨時増刊 No.19
書籍情報