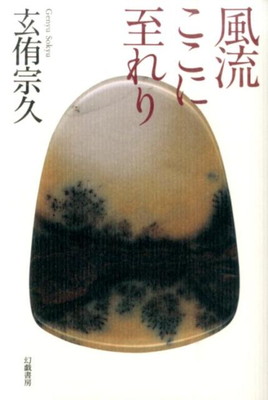浜田廣介作『泣いた赤鬼』を初めて読んだのは、小学校の三年生だったろうか。私は読みながら、泣いた。たしか青鬼が手紙を寄越し、心配した赤鬼がその家を訪ねていくのだが、青鬼は遠くへ行ってしまったらしく呼べども答えない。きっとその場面で、私は青鬼の友情に泣けてしまったのだと思う。
二度目に同じ本を読んだのは、高校に入ってからだ。私は童話研究会というグループに属していたため、いろいろ考えながら読んだ記憶がある。すると同じ本なのに、今度は泣けるどころか腹が立ってきた。だいたい赤鬼が人間の子供と仲良くしたいと望むことじたい、不埒な望みではないか。やはり同じ生き物どうしが仲良くすべきではないかと、やたら理屈っぽく反発したのである。
三度目はたぶん大学に入ってからだったと思う。そのときは、「鬼」という存在じたいが気になり、いったい「鬼」とは何か、などと考えて先に進めなかった。「桃太郎」まで憶いだし、鬼はなにゆえ苛められねばならぬのかと、考え込んだのである。
世の中には、子供も大人も読めるし楽しめる童話もある。大人だけの童話もある。しかし同じように、子供にしか感動できない童話もあるのではないだろうか。
子供の目のつけどころは明らかに大人とは違う。その年齢に応じた物語を読み、階段を上るように成長するなら、大人は感動できなくても仕方ないのかもしれない。
振り返れば、高校生のときは、なぜ『泣いた赤鬼』などに涙したのだろうと、子供の頃の自分を情けなく思い返しもした。
大学のときも基本的にその気分には変わりなく、あまつさえ浜田廣介を批判さえしたと思う。
しかし今読み返すと、むろん当時の感慨はいろいろ憶いだすものの、全体としては小学生に近い感性で読んでいることに驚くのである。
人の成長とは不思議なものだ。本というのも不思議なものだ。
そのことから想うのは、もしかすると子供が感動する本を識別できるのは、若い文学青年や少女ではなく、むしろ年期のいった高齢者ではないか、ということだ。そうだとすれば、こども図書館の活動にはお年寄りの協力こそ仰ぎたいところだ。イデオロギーや概念ではなく、お年寄りにはもっと大切で切実なものがきっと見えている。今の私は『泣いた赤鬼』を読み返しても泣かないが、もっと高齢になればまた泣けてくるのかもしれない。
2006/5/10こどもの図書館
関連リンク
書籍情報