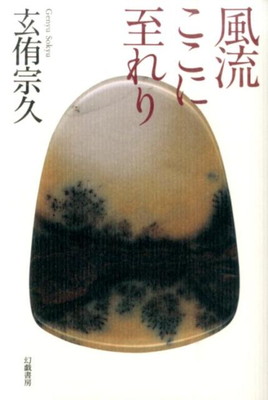精進料理と云えば、禅寺など仏教寺院に伝わるいわゆる肉魚抜きの料理を指すことが多い。しかし、どうして肉魚抜きが「精進」なのだろう。
「精進」はもともと仏教の実践法である六波羅蜜の一つ。手間暇惜しまず、結果を期待せず、という行動の在り方を意味する。しかしそれならべつに、肉や魚を嫌わずともよいではないか。仏教にとって植物と動物とは、対等のいのちなのだし……。そんな疑問は、少し仏教を学べば必ずと湧いてくるはずである。
現在のような精進料理の考え方ができるまでのプロセスを簡単に辿りながら、「精進」について考えてみたい。
もともとお釈迦さまの時代の仏教は、托鉢でいただいたものを選り好みせずに食べており、実際には穀類、豆類、木の実や果物などが多かったようだが、原則として肉食を禁じたりはしていないし、実際に食べてもいる。
『スッタニパータ』には「生き物を殺すこと、打ち、切断し、縛ること、盗むこと、欺すこと、他人の妻に親近(しんごん)すること、……これがなまぐさである。肉食することがなまぐさいのではない」とも書かれている。
当時インドでは、いわゆる菜食主義を主張する宗教も生まれていたが、釈尊はその路線をとらず、あくまでも中道的な考え方から食材についての制限は設けなかった。ただそうなると、托鉢に供するために信者が動物を殺したり鳥を絞めたりしないとも限らない。そこで、「見聞疑(けんもんぎ)の三肉」といって、その動物が殺されるところを「見」てしまった肉、その動物が自分に食べさせるために殺されたと「聞」いた肉、そしてその「疑」いがある肉を食することが禁じられた。
むろん大前提として、仏道修行者たちは「慈悲」の実践のため、自ら狩りや漁で動物や魚を獲ることはあり得ない。それどころか、不殺生戒のために、土中の虫たちを殺す農耕も厳に禁じられていたから、すべての食事は人々からの托鉢に頼っていた。ほとんどはいただいたまま、時に多少の煮炊きをすることはあったらしいが、基本的には料理も修行僧が積極的にすべきことではなかったのである。
一切の労働を禁じ、托鉢のみに頼っていたインドでの仏教は、しかし中国に渡ると一変する。なにより大きかったのは、托鉢という習慣が中国にはなかったため、自給自足するべく禅宗を中心に農耕を始めたということだろう。ことに道教の影響を受けた禅宗の場合、寺院を山奥に建立することが多かったから、破戒であっても自ら耕すしかなかったのである。
農耕がインドで禁じられていた背景には、土中の虫の不殺生だけでなく、所有や蓄財への忌避という側面もあった。仏滅百年後に起こった根本分裂でも、現金の寄付を受け付けるかどうかという大問題のほかに、塩などの調味料は保管してもよいのではないか、といった所有の詳細も問題にされた。昼前しか食べてはいけなかった食事も、余れば午後に持ち越していいではないか、といった意見まで出されている。
いずれにしても農業を始めるということは、それら些細なことが吹っ飛ぶほど、仏教にとっては大きな破戒をいくつも導く大事件だったと云えるだろう。自分たちで野菜を作り、それを調理するということは、当然虫を殺すことにも繋がるし、保管して所有することにもなる。
インドで厳禁していた労働が解禁される以上、そこには新たな考え方が必要だった。戒律が緩むだけでは面目が立たないというわけだ。
そこで現れたのが「精進」という考え方だった。これは報酬を期待しない労働とも云えるし、修行としてなされる労働と云ってもいいだろう。禅宗では「作務(さむ)」と云うが、要するに畑仕事も台所仕事も掃除や洗濯も、三昧(ざんまい)をめざす修行の一環としてなされるという意味づけである。
加えて、農耕によって否応なくなされる殺生への罪滅ぼしも必要だった。自分たちで食材を調達する以上、狩りや漁までしたのでは仏教の基本を逸脱してしまう。それを禁じるのは当然だが、さらに彼らは肉食を一切しないことで、農耕という破戒とのバランスをとろうとしたのではないだろうか。
インドでは許されなかった農業をするかわり、インドでは認められていた肉食を禁じたのである。
五世紀に作られた四巻本の『楞伽経(りょうがきょう)』や『梵網(ぼんもう)経』の規定がそのような新たな規矩(きく)の範例になっていく。たとえば『楞伽経』の末尾には、肉食がまるで親の敵のように非難され、肉を食べると、不浄になる、慈心が芽生えない、呪術が不成就になる、天に見捨てられる、口臭がする、悪夢を見るなど、凡そ考えつくかぎりの批判の挙げ句、肉を食べ続けているとやがては人の肉まで食べたくなると脅す。また『梵網経』四十八軽戒(きょうかい)の第二十戒には、「六道衆生は皆是れ我が父母なり。而して殺して食する者は、即ち我が父母を殺し、亦た我が故身(こしん)を殺すなり」と云う。「故身」とは前世の我が身のことだから、つまり肉食とは先祖や我が身を食べることだというのである。
禅宗の規矩を完成したとされる八世紀の百丈懐海(ひゃくじょうえかい)禅師は、「草を斬り木を伐り、地を掘り土を墾(たがや)す、罪の報いの相ありとせんや」とある僧に問われ、「かならず罪有りと言うを得ず、またかならず罪無しと言うを得ず。罪有りと罪無しとは、当人にあり」と答えた。ここにおいて農業は、修行のための清浄な行としてという条件付きで明確に解禁されたと云えるだろう。そしてほぼ同じ時期に、肉を食べないことも仏教の常識となっていくのである。
日本に渡来した仏教は、基本的にはそのような仏教だったと思っていい。だからこそ仏教伝来によって今後は自分たちも殺されないと喜ぶ鹿たちの、鹿(しし)踊り(岩手県)なども生まれた。その際、精進料理をすんなり受容できた背景には、神道などの「潔斎」の思想が下敷きとしてすでにあったことも重要かもしれない。六七五年には天武天皇が、勅令によって僧侶の肉食を禁じた。
『枕草子』が書かれたのは紀元千年ころ、つまり平安中期とされるが、そこにはもう「精進もの」が登場している。清少納言によれば、「そうじもの(精進もの)いとあしき」、つまり精進料理は非常にまずいと嘆いている。比叡山や高野山にはその開創当時からの精進料理メニューも残っているようだが、まだ今のように洗練されてはいなかったのだろう。
さて、だいたいの経緯はご理解いただけたと思うが、まだ当初の疑問には答えていない。つまり、肉や魚を僧侶が食べなくなった経過はわかっても、どうしてそれが「精進」なのかという問題である。
初めに私は、手間暇惜しまず、結果を期待せず、というのが「精進」の本質なのだと申し上げた。たぶん読者諸賢は、精進料理がそのくらい調理に手間暇かかることは充分ご理解されていると思う。しかし、もう一つの「結果を期待せず」というのはいったい何のことか。精進料理の精進料理たる所以は、じつはそこにこそあると思うのだが、ご理解いただけるだろうか。
一例として、コンニャクが食べられるまでの道程を辿ってみよう。
まず重要なことは、コンニャク芋という代物が、煮たり焼いたりした程度ではけっして食べられないという事実である。
食の基本に仏教徒としての「慈悲」を置くとするなら、まず我々が食べることで他の生き物の食料を奪うことは避けたい。そう考えると、食物連鎖を申し上げるまでもなく、肉はいずれきっと誰かの食べ物になるはずだと気づくだろう。少し炙った程度で人間にも美味しい肉は、だから精進からは程遠いのである。
たいてい人は、それが食べられるものであることを、鳥や獣から教わることが多い。しかしそれを真似て食べたのでは、彼らの食料を奪うことになる。だからまず、誰も食べないようなものに狙いを定めるのが最初の精進になる。「結果を期待せず」食材を探しまわるのが最大の精進なのだ。
コンニャクは、遅くとも三世紀には中国で灰汁(あく)で煮て固めて食べていたらしいのだが、あれを最初に食べ物に仕立てた人はエライ。
猪も振り向かないあんなゴツゴツした芋を、丁寧に洗って皮を適当に剥き、それを摺り下ろして鍋に入れ、そのままではエグくて食べようもないので今度はくつくつ熱してみた。そこまでしてもまだ食べ物にならない代物に、さらに灰汁を入れてみたのはヤケクソだったのだろうか。今では灰汁ではなく水酸化カルシウムを入れるが、食べるまえにはもう一度お湯で煮出し、余分なアクを追い出さなくてはならない。
仏教伝来とともに朝鮮半島から伝わったというのだから、当時は東南アジアの広い地域で食べられていたのではないだろうか。現在では日本のほか、中国の西南部(雲南省、貴州省など)で魔芋(あるいは魔芋豆腐)と呼ばれ、食習慣を残しているが、残念ながらそれ以外では殆ど見られなくなってしまった。あまりにも手間暇がかかるため、精進しきれないということだろう。
平安・鎌倉時代には、わずかに僧侶や貴族などのあいだで珍重され、コンニャクの味噌煮などは「糟鶏(そうけい)」と呼ばれて好まれたが、まだまだ一般化はしていなかったようだ。
しかし江戸時代、コンニャク芋の産地だった常陸の国(茨城県)で、画期的な発明がなされることになる。ある農民が、腐りやすくて保存が難しいコンニャク芋を、なんとかいつでも食べられるようにできないものかと日夜呻吟精進のあげく、ついに乾燥させて杵で搗き、粉にして保存する方法を編みだしたのである。感激した水戸藩の藩主は、彼に名字帯刀を許し、彼は中島藤右衛門と名乗る。
今で云うインスタントの走りだが、その「精粉」という粉の発明で、コンニャクは日本中に広まっていったのである。
なんだか熱くなって書いてしまったが、こうして見てくると、ふにゃふにゃしたあのコンニャクがじつに固い信念とたゆまぬ精進によって生みだされていたことがわかる。
今でこそ食物繊維グルコマンナンなどともてはやされているが、もともとあの芋が食べ物にもなるなんて、果たしてコンニャク芋自身、気づいていただろうか。実際今だって、コンニャク芋は食べられるだけでなく、工業用の糊にも大量に加工されている。第二次大戦中、アメリカまで飛ばされた風船爆弾も、じつは和紙をコンニャク糊で貼り付けてあったのである。
そんなふうに、しつこく手を加えることで植物自身も気づかなかった貌を引きだしてしまうことこそ、まさしく精進中の精進だろう。
思えば食べられるコンニャクを作った人間の精進もすごいが、それに身を任せきったコンニャクもエライ。
コンニャクでも豆腐でも麩でもそうだが、あそこまで無私の境地を見せつけられると、私は思わず合掌して敬意を示し、そしてそれから無性にいとおしくなってパクリと食べてしまう。コンニャクはいつだって存在感はあるのに押しつけがましくはなく、和やかに周囲に馴染みながらも迎合はしない。さすが精進を重ねた御修行の成果、という味わいなのである。
2009/04/06文藝春秋5月臨時増刊号「くりま」
書籍情報