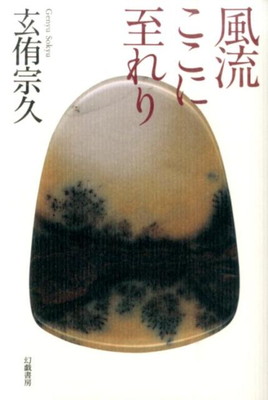大学生の頃、学校にはあまり行かず、小説を書いていた。自分の輪郭もよく分からず、「文体」にも意識は行き届かなかった。新人賞に応募しても二次選考に通らないこともあり、鬱屈した日々だった。
ところがある新人賞で最終選考に残り、その頃ちょうど、同級生だった友人が出版社に入社した。当時の編集者はまだ無名の作家の発掘にも力を入れており、「誰かいないか」という編集長の求めに、新入社員の同級生は私の原稿を持っていったらしい。らしい、というのも妙な話だが、私は彼に「編集長が会いたがっている」と言われるまで、実際そのことは知らなかったのである。
寺田博という名うての編集長に初めてお会いしたのは、春先の暖かい日だった。最寄りの駅で降り、友人の会社に向かう道すがら、私は花屋の店先で見かけた雪柳をなぜか買った。読んでもらった原稿の感想をもらうのに、花を持参する青年、というのは、かなり珍しいのだろうか。編集部に入り、挨拶もそこそこに雪柳の包みを渡すと、なにも言われなかったものの奇妙な眼差しを向けられた気がする。
それはともかく、私は寺田さんに「君はすでに文体がある」と誉められ、しかし「この第四章から文体が変わってしまうんだ」と言われ、どういうことなのかよく分からないまま、書き直しては持参し、あるいは誉め貶(けな)され、あるいは貶し誉められつつその後も何度かその編集部に通った。たしか四回目のときだったか、「宜しい」ということになり、ようやく『作品』という文芸誌への掲載が決まった。当時二十六歳だった私は、何日か有頂天の気分を味わったのだと思う。
それがどのくらい続いたのか、今となっては記憶にないのだが、その後しばらくして同級生だった友人から会社が倒産すると知らされ、とうとう掲載予定号は出なかった。
やがて寺田さんは福武書店に行って『海燕』という雑誌を始め、私は運命のようなものを感じて修行道場に入門した。そしてしばらく僧侶に専念し、また書きだしたとき、寺田さんは歴史小説の評論家になっていた。作品社は倒産は免れたが、『作品』は休刊のままだ。むろん寺田さんにとってこそ大きな出来事だったはずだが、今の私が僧侶でありつつ物を書いていられるのも、あの休刊のおかげではないか。二十代でデビューしなかった幸運を、つくづくありがたく思い返すこの頃なのである。
2010/12/15Shall we Lotte11号
書籍情報