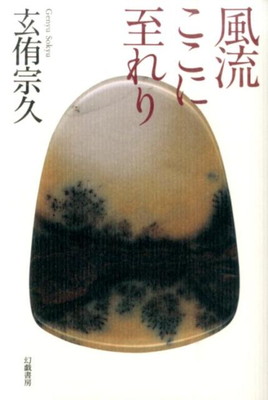白隠慧鶴禅師は貞享二(一六八五)年、駿河の国、原の宿に生まれ、明和五(一七六八)年、八十四歳で遷化(せんげ)した臨済宗の僧である。諡(おくりな)は後桜町天皇から「神機独妙禅師(しんきどくみょうぜんじ)」、明治天皇から「正宗国師(しょうじゅうこくし)」と下賜された。じつにイメージの異なる二つの諡であるが、まさしくこの幅こそが禅師の真骨頂であろうと思う。
ここに白隠禅師の全貌を描く紙幅は到底ない。ここでは二つの諡を足がかりに大凡のイメージだけを掴んでいただきたいと思う。
「正宗国師」としての禅師は、臨済宗中興の祖ともいわれ、五百年でようやく一人出るほどの傑物(五百年間出)とされる。公案体系を組み直し、自ら「隻手(せきしゅ)の声」という公案を創出し、じつに多くの出家・在家を導いたと言われる。その内容は大抵以下のようなものだ。
「両手を拍(う)てばこんな音がする。それでは片手の音とはどんなものか、とっぷり坐禅して聞いてこい」
世の中には反対語、対語が溢れている。たとえば美醜、尊卑、浄穢(じょうえ)、大小、好き嫌いなど。しかし禅では、そうした相対的比較による価値観に意味を置かない。それは脳のクセに従った分析的解釈であり、「命」の本体とは何の関係もない。もっといえば、そんな解釈は「妄想」に過ぎないというのである。
古来、そうした禅の公案の入門編には、「趙州無字(じょうしゅうむじ)」といわれる公案が用いられてきた。簡単に言えば、「犬にも仏性は有るか無いか」と問うのだが、「有」と答えても「無」と答えても老師には鈴を振られる。そうして二元論の無意味が婉曲に、しかも強烈に知らされるのだが、この公案よりも「片手の声」のほうが得心しやすいと、禅師は言うのである。
修行に公案を用いるのは臨済宗、黄檗(おうばく)宗のみで、曹洞宗は基本的に用いない。これはどういうことかというと、曹洞宗は「行持(ぎょうじ・身のこなし)」に絞って仏の作法を真似るのに対し、臨・黄では行持だけでなく心、あるいは発想法まで仏に倣おうというのである。ただ、それでは虻蜂取らずになってしまい、行持も心も中途半端になる、という側面もあるし、形だけでなく少しは仏の心の在り方も学ぶべきだと考える人々もいる。所詮、その方法論の違いは、初学者にとってのみ大きいと考えるべきかもしれない。蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)禅師はすでに「済洞(臨済と曹洞)を論ずることなかれ」と説いているし、両方の道場で修行する人々も昔は多かった。
とにかく白隠は、そうした禅の第一義の世界で、大きな功績を残した。達磨大師から脈々と伝わった禅が、当初はさまざまな流派として日本にも流れ込んだが、結果としては禅定(ぜんじょう)を最も重視する大應、大燈、関山へと伝わった禅のうち、白隠を通ったものだけが生き残る。沖本克己氏はそれを「砂時計のくびれ」のようなものだと評するが、よかれあしかれ白隠は、それゆえ臨済宗中興の祖と呼ばれるのである。
早熟ぶりを示す話や、厳しい修行に打ち込んだエピソードには事欠かない。しかし同時に、白隠には増上慢の話も数多い。越後英厳寺の性徹(しょうてつ)和尚のもとで、師匠は認めないのに「大悟」に酔いしれた姿もよく知られる。しかしたまたまそこに掛搭(かとう・入門)した宗覚(そうかく)と出逢い、信州飯山の正受庵(しょうじゅあん)に導かれることで白隠の人生は変わる。六十四歳の正受老人に二十四歳の雲水が胸ぐらを捕まれ、殴られ蹴られ、参禅のたびに「どぶねずみ」「穴蔵禅坊主」と罵倒されるのである。おそらくそこでの体験は、白隠の人の好い坊ちゃん気質を打ち砕いたことだろう。およそ半年余りの滞在だが、苦労の甲斐あり、ある雨の日の托鉢中に箒で老婆に殴られた途端、大悟したと伝えられる。
こうして白隠は、正法(しょうぼう)の担い手としての道を歩みはじめるわけだが、それまでの特筆すべき出来事は、やはり宝永四(一七〇七)年十一月の富士山噴火だろう。大音響と炎が噴き上げ、ほぼ二週間に亘って空から石や砂や灰が降り続いたといわれる。二十三歳の白隠はちょうど行脚から戻って沼津の大聖寺(初めて修行に入った寺)におり、本堂に坐禅したまま「趙州無字」に没頭していたという。
しかも修行仲間がいくら避難を呼びかけても動じなかった、というのだから困った御仁である。
白隠禅師を特徴づける言葉として、よく「勇猛心(ゆみょうしん)」が用いられるが、これも周囲の仲間にすれば、時に巨大な自我と見えはしなかっただろうか。『維摩経』には「須弥山(しゅみぜん・ヒマラヤ)のような自我も、大いなる悟りの機縁になる」と書かれているが、そう解釈するしかないのかもしれない。
ともあれ富士(不二)山を仰ぎながら育った宿場町原の駅長の息子杉山岩次郎は、大悟の末に、慧鶴という諱(いみな)の上に道号「白隠」を用いた。おそらく禅の世界観である「不二」を体現する者として「富士」を冠し、常に雪を被った気高い霊峰を「白隠(snow capped)」と表したのではあるまいか。「不二」は白隠にとって尽きせぬ上求(じょうぐ)の世界でもあり、同時に衆生に説くべき「正法」をも意味していたはずである。
さてもう一つの諡「神機独妙禅師」だが、これは主に白隠の多彩な表現行為を彷彿させる。
勇猛心でがむしゃらに邁進するかに見える白隠だが、その表現はじつに多彩で豊かである。ことに松蔭寺の住職に就き、今なら高齢者と呼ばれる頃から、どんどん禅画を描き、本格的な著作もするようになる。弟子の養成ばかりでなく、晩年はあらゆる手段を用いて檀家や信者の接化に努めたといえるのではないだろうか。
「不立文字(ふりゅうもんじ)」と言われる禅が、なにゆえ、と思われる方もあるかもしれないが、文字として固定的な原理原則をもたないからこそ、機に応じ、人に接して無限の表現が可能になる。禅僧にとっては日常こそ創作の対象。創作のなかにこそ「今」があり、「自由」があるのである。
ただ、私も小説を書くから思うのだが、白隠の表現には、圧倒的に個人に向けられたものが多い。そこがいわゆる「文芸作品」との一番の違いだろう。たとえば仮名法語の『藪柑子(やぶこうじ)』なども、六十九歳の老僧が母親の五十回忌にあたり、何か供養になることができないかと、「富郷賢媖」なる女性に向けて書くことにしたという(この名はもしや、亡母の戒名か)。しかも五月二十五日暮れ方より書きだした筆書き原稿は、翌日の夜半過ぎに書き終えている。原稿用紙にすれば二十三枚ほどだが、この迸るようなエネルギーは老僧とは思えない。
ほかにも、六十七歳のときに書いた『於仁安佐美(おにあざみ)』の上巻は、当時二十七歳と二十三歳だった中御門(なかみかど)天皇の皇女(宝鏡寺門跡および光照院門跡)に法語として与えられ、下巻は伊予大洲(おおず)藩の江戸詰家老、加藤某に与えられている。
殿様への叱責あり、庶民への励ましあり、その対機説法(たいきせっぽう)の相手も内容も、ほとんど無制限といえるほど広い。むろん、個人向けではない著作も多いが、対象の読者はきっちり考えられている。万巻の禅籍や仏教書だけでなく、白隠が『論語』『中庸』『易経』『老子』『荘子』など、あるいは漢方医学にも通暁していたのは明らかである。
しかも白隠の布教における大きな特徴は、いわば庶民信仰ともいえる古来の日本人の信仰対象を、積極的に受け容れていることだろう。地獄、極楽、天神さま、稲荷、七福神などのほか、お題目や念仏にだって垣根がない。
日本的な、あまりに日本的な禅が、ここに誕生したといえないだろうか。
そうした表現が最も顕著なのが禅画であるが、このところ白隠の禅画については、京都・花園大学の芳澤勝弘教授が画期的な発表を続けている。芳澤教授は全国各地をくまなく歩きながら、これまで贋作とされてきた多くの「白隠筆」の禅画を、禅師自身の若描きなのだと鑑定する。
芳澤教授は自ら驚きを隠しきれず、白隠の描いた禅画は「おそらく一万枚ほどあるのではないか」とおっしゃる。四十歳から描きだしたとしても、四十四年で一万枚ということは、一枚一・六日のペースだ。これが尋常でないことは、どなたにも容易にわかるだろう。それはもう、「行」と呼んでもいいかもしれない。
あらゆる人々に接し、その人に応じた教えを時にはユーモアたっぷりに描き上げる。そこでは禅の枠組みさえ、余計な制約であったかもしれない。
当時の世の中は、庶民の困窮を尻目に上流社会は享楽に耽り、政治もけっして安定してはいなかった。今の格差社会、短命政府の現状に似ているといえば似ている。そんななか、白隠は庶民に「孝」や「仁」など儒教の徳目を説き、道教的「長寿」や「和合」を勧める。また御政道批判もしっかり書き残している。
晩年の白隠には観音信仰が色濃くあり、そこには若くして喪った母親の面影があるのかもしれないが、自らにも相手に応じて無限に変化できる「応化(おうけ)力」こそを求めたのではないか。おそらくそれが白隠の求めた菩薩道の帰結であった。
白隠は『延命十句観音経霊験記』を書き、さかんにこの短いお経を唱えることを勧めた。庶民にも簡単に得られる禅定の方法であるばかりでなく、これは「観音」の思想そのものの流布でもあった。
「正法」としての純禅と、「神機独妙」としか言いようのない観音の慈悲、これが双つながら白隠を特徴づける。なんと厳粛かつポップな禅僧であろう。
2012/11/12ほんとうの仏教入門(中央公論新社)
書籍情報