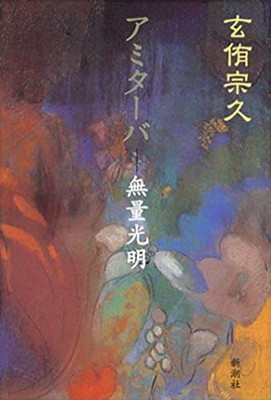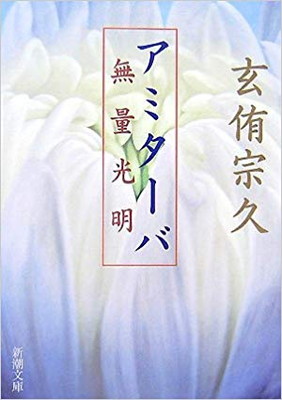臨済宗僧侶という立場上、特定の死生観を奉じていると思われるかもしれないが、むしろ逆である。つまり、多くの人々に戒名をつけ、引導を渡すことを仕事にしているため、故人それぞれの人生上のテーマを探し、それを肯定しなくてはならない。禅的な死生観ですべて事が済めばラクだが、実際には儒教、道教、神道的な考え方、あるいは今どきの宗教由来でない考え方も、故人の生き方を肯定するためには必要になってくる。この仕事をしていると、じつは死生観のデパートみたいな状態になるのである。
たとえば禅の死生観と言っても、それは一様ではない。白隠慧鶴禅師のように遺偈(ゆいげ)も残さず「大吽一声」で亡くなった方もいれば、仙厓義梵禅師のように「死にとうもない」と呟いた方もいる。
仙厓さんの遺偈は、基本的に禅の立場をうまく語っていると思うので紹介しておこう。「来時知来処 去時知去処 不撒手懸厓 雲深不知処」。地元博多の野口善敬師の訳で味わっていただこう。「この世に来た時に、どっちから来たか知っとらっしゃったごと、去る時にもどっちに行きんしゃあか分かるくさ。ばってん、今、崖っぷちにぶらさがっとって、手ば放されんけん、雲が深うて、行き先がよう見えんばい」。
どうにも情けなく聞こえるかもしれないが、これはある意味どんなときにも予断をもたぬ、という意味で極めて禅的である。「行き先が見えない」と確かに仙厓は言うが、そのことが不安だというのではない。誰にとっても先が見えないのは当然のこと。むしろ仙厓はそのことを昂然と主張するのだ。済んだ過去は悔やまず、未来は憂えず、ただ今だけに没頭するのが禅的生き方であり、死に方だと。
そこから芭蕉の句「やがて死ぬけしきは見えず蝉の声」も生まれた。七日後には確実に死ぬというのに、死ぬ直前まで死を意識せず(しないかのように)ミンミン・ジージー鳴く蝉が、天晴れだというのである。また「浜までは海女も簑(みの)きる時雨(しぐれ)かな」という瓢水和尚の句もある。この場合は、どうせ濡れるのだから、簑など要らないというある種投げやりな姿勢が戒められる。死の直前まで不安に怯えたり捨て鉢な気分にならず、従容としかも丁寧に生きることが勧められるのである。
しかしそうは言っても、先のことは「分からない」で済ませられないのが人間である。あるいはキリスト教の天国に希望を見いだし、あるいは仏教の浄土を欣(ごん)求(ぐ)することもあっていいだろう。アメリカのターミナルケアの場では、チベット密教の「純粋な光になる」というイメージが人気だが、これもいわゆる「臨死体験」に沿った一般化しやすい死への導入である。
私は以前、『アミターバ 無量光明』(新潮文庫)を書いたが、これは死に行く人が阿弥陀如来の原イメージである「無量光明」に入っていく物語である。酸欠状態に強い網膜内の円錐細胞の働きで、おそらく人は臨死のとき、このような体験をするのではないか。それは今も私のなかで保たれている重要なイメージである。
浄土といい天国というと、さまざまな定義があって面倒くさい。というか、宗教宗派の考えに左右されるため、厄介なのだ。たとえばウェールズ生まれのC・W・ニコル氏は、子供のころ飼い犬が死にそうになり、悲嘆に暮れて教会に行って祈りを捧げていると、教会の牧師に祈りの内容を訊かれたという。少年は正直に、「犬がもう死ぬから、先に天国に行って、僕がいい子だったら天国で会いたい」と答えたのだが、牧師はなんと「犬は天国に行かない」と言ったそうだ。ニコル少年は「犬がいない天国には行きたくない」と叫び、牧師に顔を叩かれた。更に少年は「神さまなんて大嫌い。神さまのバカ」と怒鳴って教会から駆けだしたというのだが、なんと悲しい話だろう。教義そのままでは箇々の死生観にはなり得ず、救済もできないという典型的な例だろう。
幸い彼の祖母が「神さまはバカじゃない」と宥め、そして「犬も生きているでしょ。生きているということは、神様の息がかかっている。全ての生き物がいなくちゃ天国じゃないでしょ」と、ニコル少年の思いを踏まえた天国を示してくれた。彼女こそ救い主である。
日本の浄土教の示す浄土も、その意味では些か不備だ。なにより浄土とは、穢(え)土(ど)の反対語であるから、まずは概念としか思えない。詳しく知ろうと思って経典を読んでもあまり魅力的な描写がなく、とても行ってみたいとは思えないのだ。
どこに行くのか、という問いに対しては、天国も浄土もじつはあまり人気がない。日本人の口から最も一般的に聞かれるのはやはり「あの世」だろう。これは仏教語でないばかりか、誰が使いだしたのかも分からないが、「あの」で指示されるということは、お互いよく知っている場所、つまり「往く」のではなく「還る」場所なのだと気づく。おそらく日本人は、死んでから知らない場所には行きたくないのだろう。懐かしい「あの」場所に還りたいのだ。
死生観という言葉は、一九○四年、加藤咄堂が同名の書籍を刊行して世に出た言葉である。加藤氏自身は武士道的死生観をあらためて提出したように思えるが、それ以後、柳田國男や折口信夫が民衆のなかの死生観を炙りだしていく。
あの世として、我々のごく身近な海や野山が想定されるのは、確かに人情に沿っている。その点で二人の思いは重なったと思える。死者は亡くなってもその辺で見ている存在、というのが二人に共通の考え方だった。しかし問題は、死者には生前と同じ個性が保たれるのかどうか、である。これは仏教の浄土に往くのが「誰か」という問題にも重なるのだが、柳田國男は個性が「残る」と考え、折口信夫は「残らない」と考えた。それは今日まで後を引く死生観上の大問題である。
人々がなにを願い、どう思っているのか、と考えると、軍配は自ずと柳田説のほうに上がるような気がする。現在でも、葬儀での弔辞などを聞くかぎり、彼らは「向こう」に還っても、同じように好きなビールを飲み、先に還った親や配偶者と再会して楽しく語らうようなのである。それを願う人情はなるほど分かる。しかし問題は、それなら「成仏」とは何なのか、ということである。
私自身は「仏」を「ほとけ」と訓んだのは「ほどける」に由来すると考えている。神は「むすび」、仏は「ほどける」。この訓みは、仏教の解(げ)脱(だつ)にも即していてじつに秀逸だと思う。しかしそうなると、引導を渡す場合にも「木っ端微塵」になって個性を失わせてはいけないような気がする。せいぜい「東西南北、汝の去るに任す」程度に収めないと、やりすぎに思えてしまうのである。死は世につれて変化するのだし、仕方ないとは思う。しかし、それゆえ日本には幽霊が多く温存される気がするのも、これまた仕方ないのだろうか。
戦後の復興期や高度経済成長期にかけて、人々はまるで死なないかの如く、死を隠蔽ないし忘却して働いてきた。しかし最近は、増え続けるガン死や災害死のせいか、誰もがある種の死生観を求めているのを感じる。「生」も「死」も個人化し、ありあわせのパッケージでは間に合わないのだろう。
私自身は「死にとうもない」と言うかもしれないが、檀家さんを送り出すにはそれでは困るので、本当に困る。
2016/07/18新潮45
書籍情報