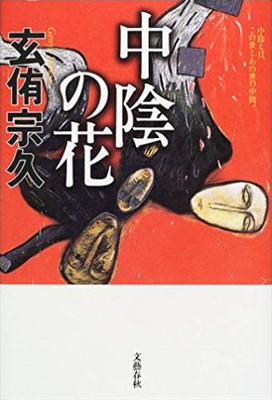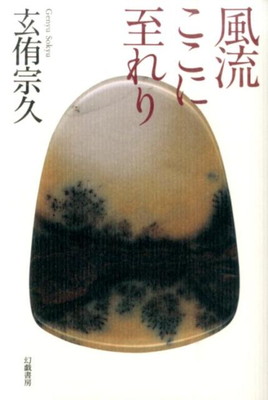中陰の花が咲き、芥川賞を受賞してしまった(二〇〇一年)。すると全国あちこちの和尚さんたちからたくさんの手紙が届いた。単に喜びと激励の手紙もあるが、多くは「じつは自分も永いこと小説を書いていて……」というもので、そうした潜在している僧侶小説家がけっこういることに驚いた。本門仏立(ほんもんぶつりゅう)宗、日蓮宗、天台宗、そしてわが臨済宗もいた。
考えてみれば驚くには値しないのかもしれない。我々が毎日よんでいるお経という文章は、なかなかに哲学的であり、また文学的である。少なくともそれは何百年、ものによっては二千年ほどの年月を生き延びてきた。それだけの力があるということだろう。
聖書を文学として読み直すという作業が最近起こっているが、お経もそうした読まれ方に十分堪えるものではないだろうか? そのことと僧侶小説家の存在がどう関係するかは判らないが、今後はお経も、文学的に翻案されていいのかもしれない。
文学的、ということは個別的ということだろう。個別的すぎれば万人が繰り返し唱えるようなものではなくなってしまうが、お経の心はもっと多くの人に読み物として読まれ、現代人の心に沁みていく工夫が待たれているような気がする。
たとえば千手観音や十一面観音のお経から、そうした奇形の仏像が生まれた物語を現代風に考えてみたり、また薬師如来として人々を癒すキャラクターを現実のなかで想定してみたり。またたとえば『観音経』で示される様々な災難とそこからの脱却も、今なお充分深刻で劇的な物語を提供してくれるはずである。
「夜叉」や「人非人」を「テロリスト」と読むことも文学的想像力のなかでは可能だし、「為人所推堕(いにんしょすいだ)」で飛行機の激突を想うこともごく普通の連想だろう。そのとき「観音力」を熟考することで、また新たな文学が生まれるのではないだろうか?
手紙をくださったなかには自分はもう七十歳をすぎており、諦めたと仰る方もいたが、日々の接化(せっけ/教化・指導)のなかではそうした想像力こそ重要なのだと思う。
小説家志望の僧侶だけでなく、どなたにもお経を、もう一度想像力豊かに読み直してほしいと思うこの頃である。
※このエッセイは「風流ここに至れり」に収録されました。
2002年THE ZEN 雪山号
書籍情報